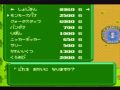邦楽ニューウェーブ
「邦楽ニューウェーブ」を捉えた一枚である。
これは邦楽がPOPSとの接近を果たした1990年頃から始まるムーブメントで、現在も多くの実力者が音楽の可能性を求めて様々な曲を生んでいる。
安易に邦楽器を使っただけの音楽ではない。
古典邦楽をやらせても右に出るものはいないほどの腕を持つアーティストが結集している。グルーブ感溢れる津軽三味線や、自由な旋律が巡りに巡る能管など、古典の閉塞感を見事に打ち破っている。その一方で、平均律によらない微妙な音程の上下など、邦楽的な豊かな響きをも見せる。
日本音楽は歴史を通して外来音楽の刺激を絶えず受け続けてきた。その中で潰えるのでは決してなく、外来音楽を新たな土壌とすることで多様性を保ち、何度も逞しく生まれ変わってきた。その日本音楽が今まさに変化の渦中で感動を巻き起こしているということを、知ることの出来る作品である。

キャンセルされた街の案内 (新潮文庫)
10編からなる短編集。
最初の「日々の春」は新入社員が気になる先輩OLの話で、どこかほんわかとした気分にさせてくれるものだったが、続いて読み進めるうちにだんだんと不消化感を感じるようになった。確かに「流れては消える人生の一瞬を鮮やかに切りとった」短編集と言えばそうなのだが、話に起承転結がなく何を言いたいのか分からない話が多いと感じた。
タイトルの「キャンセルされた街の案内」は長崎の軍艦島の話で、小学校の頃すでに廃墟になった軍艦島に行ったことがあるので、興味を持って読んだのだが、やはり今一感が残ってしまった。主人公が書いている小説の部分と実際の部分が一緒になって混乱してしまったのも一因だろう。

あの空の下で (集英社文庫)
飛行機の旅は、チェックインだパスポートコントロールだ、やれ靴を脱げだジャケットを脱げだといわれとばたばたと50,100とあるゲートから自分のゲートへ向かい、席にたどり着くまで、ただの移動であるのに、なんだか大変で不自由である。仕事がらみでのフライトであれば緊張しているし、家族を案じてフライトする事もある。
飛行機に乗っても、やれモバイルは消しなさい、荷物、そこはだめ、コンピューターはまだ使ってはいけませんといった指示に神妙に従っているしかない。
そんなときに、心ほぐされるのが結構機内誌なのである。
その機内誌での連載をのせたこの本。吉田の書く一つ一つの短編は、かりかりした気分をさらりとかわすかのようにあくまでも程よくライトなタッチで書かれてよい。しかも、ライトなタッチであっても一つ一つの作品に、しっかりとメッセージがあり、胸がじんとする。それが吉田修一の才能なのである。
多くの短編の中でも、私のお気に入りは、”東京画”。学生時代からの友情が時と環境によって関係がかわってくる話だ。“親友かといわれれば、堂々と「そうだ」とうなずけない所もあるが、......二人揃って「まさかこんな奴と」と、堂々と否定できるくらいきっと親友だったのである”。この作品には、学生から大昔学生だったそれぞれの読者がきっと、ほんの一時、時を超えさせる力がある。
エッセイでは台北での旅がよい。地元のおばちゃんが言葉の違い等におかまいなしに、“口が汚れているから拭いていきなさい”を伝えようとする。グローバル等というまでもないような、素朴な人の優しさを感じる事ができ、感謝する作者に好感を抱く。
どの作品も、人が寂しさやふがいなさのなか生きている事を見守りつつも、時や場所を超えて届く、ひと雫ずつの愛や友情のあかしをさりげなく見せられることによって、ちょうどいいくらいに少しだけ心地よくしてくれる。

太陽は動かない
日本・中国を舞台に、世界規模の利権を巡って、各国のスパイが暗躍!帯では「ノンストップ・アクション超大作」となっているが、その限りにおいては、☆5つなんだが。。。
「スパイ活劇」には成り得ても、「スパイ小説」には成り得ていないと書かざるを得ない。
端的に言えば、ディテールが甘く、リアリティが失われているところが目立つということ。
画期的な発電システムとかエネルギーを巡るデータがムチャクチャで、業界人でなくとも、3.11以降は発電規模とか分かる人も多いのだから、これは興醒め。現在の何百倍もの効率のソーラパネルとかマイクロ波ってフィクション自体は受け容れてもいいんだけど、その脇が甘いから、フィクションというよりホラにしか聞こえない。
リアリティある企業小説や産業サスペンスを扱う作家に黒木亮や高杉良あるいは池井戸潤などがいるが、彼らの共通項は、実際に大きなプロジェクトを扱うビジネス世界に身を置いていたこと。差別的な言い方をするつもりはないが、本作を書いた吉田修一には、そうした経験がない。人物描写やストーリー展開は流石の出来なだけに、本当に残念だ。
手島龍一は自著「スギハラ・ダラー」を”インテリジェンス小説”と位置付け、その定義を「公開情報や秘密情報を精査、分析して、近未来に起こるであろう出来事を描く小説」としている。この”精査・分析”が本作では不十分であり、それは作者や出版社にも自覚があるからだろう「アクション大作」と銘打つわけである。
幸いなことに、手島龍一がいくら精進しても本作のようなアクションやエンタテイメントで傑作は書けないだろうが(これは批判ではない)、吉田修一はインテリジェンスに磨きをかけることで、本作を踏み台としたインテリジェンス×エンタテイメントの傑作を書ける力量がある。次回作が楽しみである。
ただ、詰めの甘さは、瑣末な部分にもある。取材をした香港は、その成果をドヤとばかりに描写していて、それはいいのだが、料理に詳しくないようなのが残念。香港の食堂といえば、どう考えても広東料理なのだが、そこで「何か出して」と頼んで、出て来たのが、「豚の角煮」「鶏の冷製」「茹でた海老」。これじゃ日本の中華料理屋(苦笑)最初の2品は上海料理系の定番で、広東料理なら煮るのは牛バラ、鶏は揚げる。それから、「豚の角煮」じゃなくて「東坡肉」と書いてもらいたい。
コアな部分がフィクションであるからこそ、ディテールにリアリティを満たすことで、コアのフィクションにリアリティが生まれるというところを見落として欲しくない。
他のレビューで「ミッション・インポッシブル」と評していた方がいたが、そのレベルの感性で構わないなら5☆なんだけど、この作者でここまで取材したなら、そのレベル(子供騙し)で終わってはいけない。できる作者だからこそ、☆を1つ落とした。