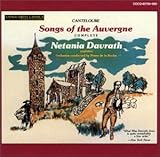
カントルーブ:オーヴェルニュの歌
ジョセフ・カントルーブのオーヴェルニュの歌を、ウクライナ出身でイスラエルに帰化したネタニア・ダヴラツが歌う。このダヴラツ盤が、オーヴェルニュの歌の初の全曲盤だった。
また、その追補としての南仏民謡集も、他の録音ではなかなか見当たらないだけに、貴重である。
カントルーブがオーヴェルニュの民謡につけた芳しき伴奏は、ピエール・ド・ラ・ローシュ(南仏民謡集では、ガーション・キングスレー)の指揮するスタジオ・オーケストラが演奏している。後の人たちが録音した伴奏に比べると、随分と荒っぽい伴奏だが、その荒っぽさが、却って民謡としての臨場感を生んでいる。雑然としているようで、勘所をしっかり押さえているので、ダヴラツの歌唱の邪魔にはならず、むしろ独特の風合いを与えることに貢献しているといえる。
ダヴラツの歌唱は、フェルメールの「牛乳を注ぐ女」を想起させるような、純朴で生活感を感じさせるもの。伴奏の雰囲気も相俟って、それが非常に魅力的に聴こえる。
美しい情景よりも先に、オーヴェルニュという土地で生活する人の暮らしを想わせる、説得力のある歌唱である。
有名なバイレロも、声の伸びやかさよりも、生娘の素朴な可愛さのイメージが先に立つ。
カントルーブのオーヴェルニュの歌の全曲盤といえば、この録音を愛でてきた人は多い。
しかし、新しい録音が現れようと、この録音の魅力を減じることはないだろう。

カントルーブ:オーヴェルニュの歌他
ジョセフ・カントルーブのオーヴェルニュの歌の全曲と、モーリス・エマニュエルの民謡由来の歌曲を詰め合わせたアルバム。
カントルーブは、ヴァンサン・ダンディの門下で、フランスの地方文化の研究に熱心に取り組んだ人であった。
そのカントルーブのライフワークとされる作品が、この5集からなるオーヴェルニュの歌である。第4集まで、1924年から1930年の間に編集されたものの、第二次世界大戦のため、最後の第5集は、カントルーブが亡くなる二年前に当たる1955年に発表されたのであった。
エマニュエルは、レオ・ドリーブの門下生だが、師匠と折り合いが悪く、教会旋法やオリエンタリズムに拘るエマニュエルは、ドリーブから破門同然の扱いを受けることになった。
自力で作曲家としての道を歩んだエマニュエルは、ブルゴーニュ地方の民謡に興味を持ち、カントルーブのような手法で、それらの民謡を編纂したのであった。
カントルーブらのフランスの民謡編纂は、その伴奏の華麗さが批判の槍玉にあげられたが、カントルーブは、民謡が歌われた土地の風合いを感じてもらうために必要な措置だと考え、亡くなるまでその方針を譲らなかったという。
結果として、民謡研究の成果としてだけでなく、優れた芸術歌曲として、多くの歌手たちがレパートリーに入れて歌っている。
アメリカ人ソプラノ歌手であるドーン・アップショウは、これらの歌曲の優れた歌い手の一人である。彼女がアメリカ人で、フランスの音楽など分かるわけがないという憶測に基づいて、このCDを無視するのであれば、それは賢明ではないし、もったいないことである。
彼女の歌唱は、オーヴェルニュ地方が空気の澄んだ美しい土地柄で、そこに住む人々も純朴なのだろうという想像を掻き立てる。
カントルーブの美しい伴奏も、そうした想像を立ち上らせることに一役買っているのだが、ケント・ナガノの率いるリヨン歌劇場のオーケストラの、こまかく神経の行き届いた演奏が、アップショウの歌唱の魅力を倍加させてくれている。
この演奏を聴くことで、オーヴェルニュ地方に行き、その風景を見て、そこの人々に会って親しく話をしたような気分にさせてくれるのだ。
フランスの田園風景を、耳で楽しむことができるというのは、なんとも贅沢な話だ。






